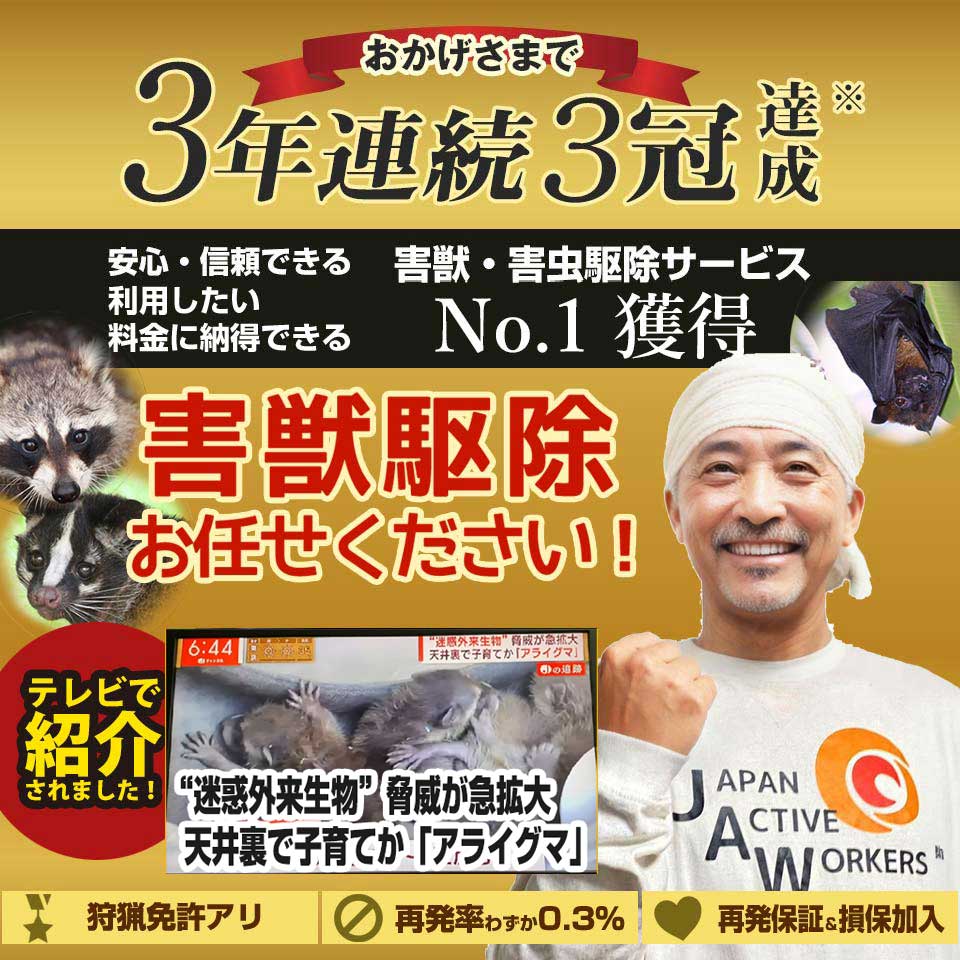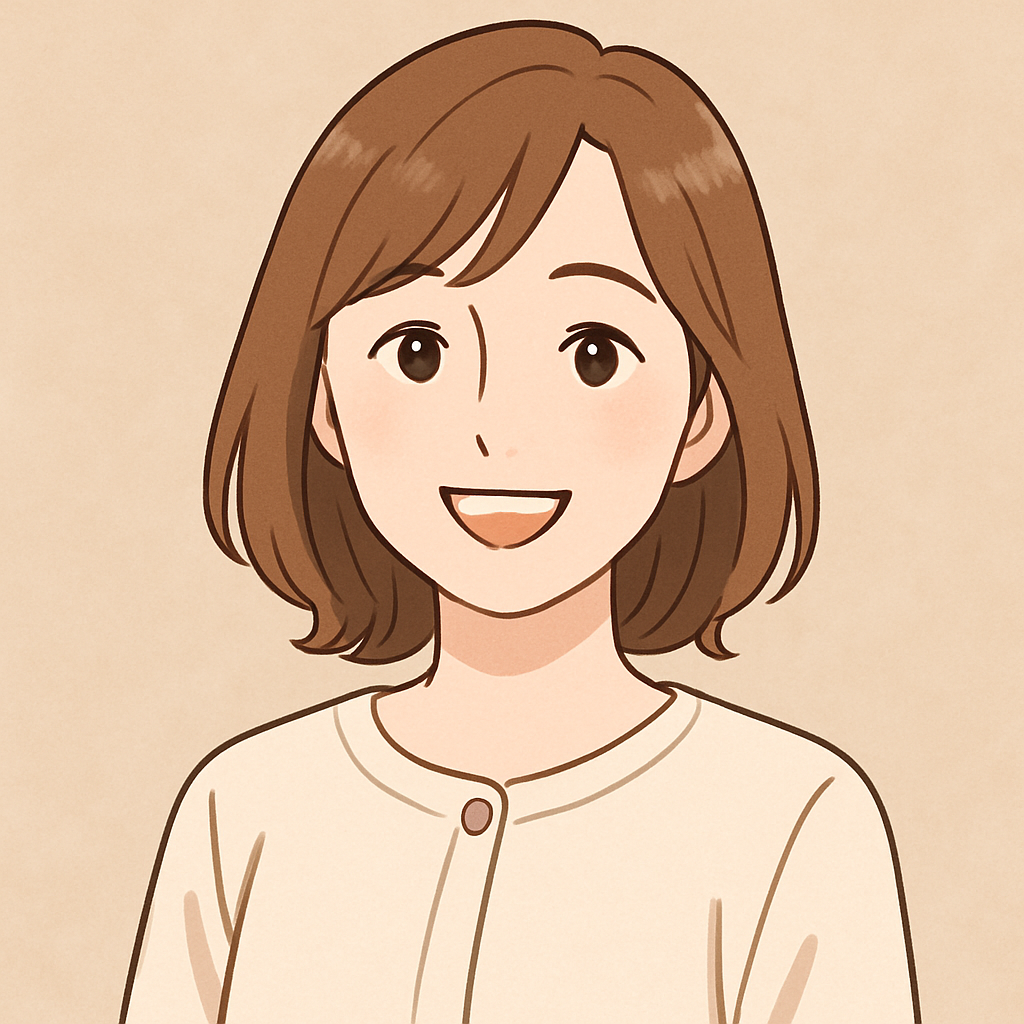近年、マダニによる感染症「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」の死亡例が全国で報告されています。中でも、アライグマやハクビシンといった害獣がマダニを媒介している可能性が指摘されており、都市部や郊外でも感染リスクが高まっているのです。
この記事では、最新の死亡事例やマダニが媒介する感染症の危険性、関東エリアでの行政対応などを含め、害獣駆除の重要性について詳しくご紹介します。
SFTSによる死亡事例が相次ぐ|YouTube報道の概要
獣医師がネコの診察後にSFTSで死亡(岡山県:2025年6月報道)
岡山県で勤務していた男性獣医師が、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)を発症し死亡するという衝撃的な事例が報道されました。感染経路は、診察を行ったネコに寄生していたマダニと見られており、発熱、下痢、血小板減少、多臓器不全といった症状が急激に悪化したとされています。
この獣医師は、ネコとの接触後すぐに体調を崩し、呼吸困難などの症状を訴えて入院しましたが、わずか数日で亡くなられました。治療が間に合わなかったことから、SFTSの進行スピードと重症度の高さが改めて注目されています。
今回の件は、獣医師やペットに関わる職業の方々だけでなく、家庭で動物を飼っていたり、害獣被害に遭っている一般の人々にも、マダニ対策の必要性を強く訴えるものです。動物が媒介する感染リスクへの理解と、早期の対応が命を守る鍵となります。
引用元:CBCニュース「ネコを治療した獣医師が死亡 マダニが媒介する感染症か 呼吸困難などの症状で救急搬送 三重」
60代女性がマダニに刺され死亡(香川県|2025年6月報道)
香川県三豊市では、農作業中にマダニに刺された60代の女性が、SFTSを発症して死亡するという深刻な事例が報告されました。
女性は数日後に発熱と倦怠感を訴えて病院を受診し、検査の結果、血小板の著しい減少と臓器機能の低下が判明。
集中治療が行われましたが容体は急速に悪化し、感染から約2週間で死亡に至りました。
2025年に入って香川県内で4件目となるSFTS死亡例であり、県は特に高齢者や農作業従事者に向けて、防虫対策の徹底や体調異変時の早期受診を強く呼びかけています。
こうした事例は、日常の延長にある自然との接点でも感染リスクがあることを再認識させるものです。
引用元: KSB瀬戸内海放送「マダニにかまれた60代女性が死亡 香川県で4例目 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)を発症」
70代男性がSFTSで死亡(熊本県|2024年6月報道)
熊本県葦北郡に住む74歳の男性が、マダニによるSFTSに感染し死亡したと報道されています。活動期の春〜初夏に発生した2024年になって初のSFTS死亡例でした。
男性は森林や草地で過ごした後に倦怠感・発熱を感じ、医療機関を受診しました。その際には異常なしとされて帰宅後も症状が進行し、再受診でSFTSと判明。その後亡くなったとされています。
この事例は、高齢者を中心に重症化リスクが高まるSFTSの実態を改めて示すものであり、草地や森林での活動における長袖長ズボン・防虫剤の使用・体調不良時の即時受診の必要性を浮き彫りにしています。
引用元:KKT熊本県民テレビ「【マダニ感染症】74歳の男性がSFTS感染し死亡 熊本市の男性は日本紅斑熱で入院」
マダニやその他のダニが媒介する感染症とその症状

SFTS
SFTSは、マダニが媒介するウイルス性の感染症で、潜伏期間は6〜14日間とされています。
感染後は、発熱、倦怠感、嘔吐、下痢といった症状が現れ、初期段階では風邪や胃腸炎と誤認されることもあります。症状が軽く見えるため、受診が遅れがちになる点にも注意が必要です。
進行すると、血小板や白血球の急激な減少、肝機能障害、さらには多臓器不全を引き起こす危険な疾患です。特に高齢者や免疫力の低い人は重症化しやすく、致死率は10〜30%に達するとも言われています。
現在のところ、SFTSに対する特効薬やワクチンは存在せず、治療は対症療法が中心です。そのため、マダニに刺されないようにする予防策が何よりも重要であり、発熱や異変を感じた際は、早めの医療機関受診が命を守るカギとなります。
日本紅斑熱
日本紅斑熱は、ダニに刺されることによってリケッチアという細菌に感染して発症する病気です。 主に西日本を中心に報告されていますが、都市近郊や関東でもまれに発生しており、注意が必要です。
感染すると発熱、発疹、刺し口の潰瘍(痂皮)などが現れ、悪寒や筋肉痛、関節痛などの全身症状を伴うこともあります。 重症化する例はまれですが、免疫力が低い方や高齢者では重い症状が出ることもあり、油断できません。
治療にはテトラサイクリン系抗菌薬が有効とされていますが、発症初期に適切な治療を開始することが非常に重要です。 そのため、ダニに刺された痕や発熱・発疹が現れた場合は、すぐに医療機関を受診するようにしましょう。
ダニ媒介脳炎
ダニ媒介脳炎は、マダニに刺されることで感染するウイルス性の中枢神経系疾患です。 ヨーロッパやロシアなどを中心に報告されてきましたが、日本国内でも北海道で感染が確認されており、油断できない感染症です。
感染すると、数日から2週間の潜伏期間を経て発熱、頭痛、嘔吐、筋肉痛などの症状が現れます。これらが治まった後に、急激に意識障害、けいれん、運動麻痺といった重篤な神経症状に進行するケースがあります。
致死率が高く、回復しても後遺症が残ることが多いため、予防が極めて重要です。有効なワクチンが存在しますが、国内では一般的に接種されていないため、マダニに刺されないための物理的な防御策が最も重要な予防手段とされています。
ライム病
ライム病は、マダニが媒介するボレリア菌によって引き起こされる感染症です。 感染初期には、発熱や倦怠感、頭痛、筋肉痛など風邪に似た症状が現れますが、特徴的なのは「遊走性紅斑」と呼ばれる輪状の赤い発疹です。
放置すると、数週間から数か月を経て神経障害や関節炎、心疾患などの合併症を引き起こす可能性があります。特に顔面神経麻痺や多発関節炎などが起こると、日常生活に大きな支障が出ることがあります。
幸いにも、ライム病は早期に診断され、抗生物質(主にドキシサイクリンなど)で治療すれば予後は良好です。マダニの刺し口に異変を感じたり、体調に変化があった場合はすぐに医療機関を受診することが大切です。
つつが虫病(マダニではありませんが参考に)
つつが虫病は、ツツガムシというダニが媒介するリケッチア属細菌によって引き起こされる感染症です。 感染すると、発熱、発疹、刺し口の潰瘍(痂皮)、筋肉痛、リンパ節の腫れなどの症状が現れます。
高齢者や基礎疾患のある方では重症化することもあり、早期治療が非常に重要です。放置してしまうと、肺炎や多臓器不全といった深刻な合併症に発展する危険性があります。
診断には血液検査が有効で、治療にはテトラサイクリン系抗生物質が使われます。自然豊かな場所に出かける際は、長袖・長ズボンの着用や防虫スプレーの使用など、ダニに刺されない工夫が必要です。
| 感染症名 | 主な症状 | 致死率 |
|---|---|---|
| SFTS(重症熱性血小板減少症候群) | 発熱、倦怠感、下痢、血小板減少、多臓器不全 | 約10〜30% |
| 日本紅斑熱 | 発熱、発疹、刺し口のしこり、関節痛 | ~2% |
| ダニ媒介脳炎 | 高熱、頭痛、意識障害、けいれん | ~20% |
| ライム病 | 倦怠感、輪状紅斑、神経障害、関節炎 | 低(治療で予後良好) |
| つつが虫病(ツツガムシ媒介) | 発熱、発疹、刺し口の潰瘍、筋肉痛 | 数%(高齢者に注意) |
アライグマ・ハクビシンとマダニの関係性

害獣が媒介源になる仕組み
アライグマやハクビシンは、山林や河川敷など自然環境に多く生息しています。 これらの害獣は、体毛にマダニを付着させた状態で移動するため、人間の生活圏へマダニを持ち込むリスクがあります。
特に、夜行性で行動範囲が広いこれらの動物は、人目につかずに住宅の屋根裏やベランダなどにも入り込むことがあり、知らぬ間に接触の危険性が生まれます。
マダニは一度侵入すると繁殖力が高く、室内での駆除が困難になるため、媒介源となる害獣の侵入防止が重要です。
生息場所と感染拡大リスク
アライグマやハクビシンは、天井裏、床下、倉庫、物置といった閉鎖的かつ人の目が届かない場所を好んで棲みつきます。 これらの空間は、マダニにとっても快適な繁殖環境となりやすいのです。
放置された巣の中では、マダニやノミなどが繁殖し続け、周辺への感染拡大を引き起こす可能性があります。被害は知らぬ間に進行し、気付いた時には大掛かりな駆除が必要になるケースも。
そのため、物音や糞尿の異臭など、異常を感じたら早めの点検と専門業者への相談が勧められます。
都市部での出没が増加
近年、森林伐採や宅地開発により、害獣の生息域が人間の生活圏と重なるようになってきました。 その影響で、アライグマやハクビシンが都市部の住宅街や公園でも頻繁に目撃されるようになっています。
こうした都市部での出没により、マダニの媒介感染症リスクが郊外や市街地にも広がるようになりました。とくに子どもや高齢者がいる家庭では、健康被害への懸念が高まっています。
害獣の出没が確認された地域では自己判断での対応は避けるべきで、専門業者による駆除や防除がおすすめです。
都市部のマダニ・SFTS感染例と行政の対応

千葉県|関東で初めてSFTS確認
千葉県南房総市では、2021年に関東で初めてSFTS(重症熱性血小板減少症候群)の感染者が確認されました。 このケースでは、感染者が農作業や山林での活動中にマダニに刺された可能性が高く、数日後に発熱や倦怠感などの症状を訴えて受診した結果、SFTSと診断されました。
この事例は、関東地域でもSFTSのリスクがあることを示しており、都市部住民にも注意喚起が必要です。特に自然に触れる機会の多い人々は予防意識を高めるべきでしょう。
千葉県では公式サイトを通じて、感染経路や症状、予防方法についての情報発信を強化しており、地域住民に対して注意喚起を行っています。 (参考:千葉県「ダニ媒介感染症について」)
東京都世田谷区|啓発ポスターや予防案内を実施
世田谷区では、春から秋にかけてのマダニ被害の拡大を防ぐため、予防啓発活動に力を入れています。 区内の公園や公共施設には、虫よけスプレーの使用や帰宅後の身体チェックを促すポスターが掲示されています。
この取り組みは、公園利用者や家庭菜園を楽しむ高齢者層に特に効果があり、日常的なマダニ対策の啓発に役立っています。
また、区のウェブサイトでもマダニ感染症に関する情報提供がされており、住民がセルフケアを実践できるよう配慮されています。(参考:世田谷区公式「マダニによる感染症(SFTS)にご注意ください」)
茨城県|感染症対策情報の更新と注意喚起
茨城県では、マダニが媒介する感染症であるSFTSやつつが虫病への注意喚起を積極的に行っています。 県内の農業従事者や登山・釣りなどアウトドア活動を行う人々に向けて、リスクと予防方法を伝える資料を配布しています。
加えて、マダニ被害の報告があった地域の住民には、防虫対策の重要性や発熱後の早期受診について個別に案内が行われることもあります。
県の感染症情報センターでは、感染者数や症状例のデータを随時更新し、地域ごとの対策に役立てる体制が整備されています。(参考:茨城県感染症情報センター「ダニ媒介感染症に注意しましょう」)
埼玉県|森林利用者や家庭菜園層へリーフレット配布
埼玉県では、森林や市街地近くに生息するアライグマやハクビシンなどの害獣がマダニを媒介する可能性を踏まえ、広く注意喚起を行っています。 県内の森林レクリエーション利用者や家庭菜園を営む高齢者層を中心に、リーフレットや啓発ポスターを配布しています。
また、住宅地周辺での害獣の目撃情報も踏まえて、感染拡大のリスクについての周知も図られています。症状の早期発見と受診の重要性が繰り返し強調されています。
県の公式サイトでは、マダニの活動時期や生息環境、刺された際の対処法について、図解付きでわかりやすく解説されています。(参考:埼玉県 SFTS・マダニ感染症対策情報)
害獣駆除が感染症予防につながる理由

被害を受けてからでは遅い
SFTSをはじめとするマダニ媒介感染症は、発症後の治療が難しく、重症化すると命に関わる重大なリスクになります。 特に高齢者や基礎疾患を抱えている人は、致死率も高く、早期の対応が何よりも重要です。
感染してしまってからでは治療法が限られてしまい、後遺症が残るケースもあります。マダニが媒介する感染症の多くはワクチンや特効薬が存在せず、重篤化する前に予防するしかありません。
そのため、「かもしれない」と感じた時点で、すぐに駆除や点検などの行動を起こすことが、健康を守る最大の手段になります。
駆除業者による包括的な対応が可能
専門の害獣駆除業者は、単なる動物の追い出しだけでなく、巣の撤去やフンの清掃、ダニの発生源となる汚染場所の消毒まで一貫して対応できます。
さらに、マダニや害獣の再侵入を防ぐために、屋根や床下の隙間を封鎖する物理的な対策も講じられます。これにより再発のリスクを大幅に減らすことができます。
市販品による自己対処に比べて安全性・効果ともに高く、時間や費用の面でも長期的に見ると効率的です。
感染症の連鎖を断ち切るための根本対策
アライグマやハクビシンといった害獣は、マダニだけでなく、レプトスピラ症や回虫などの別の病原体も運ぶリスクがあります。
害獣の存在を放置することは、マダニの生息場所を残すことに直結し、近隣住民やペットへの被害も懸念されます。地域ぐるみでの対策が必要です。
根本的な対策として、害獣の駆除と侵入口の遮断を行うことで、感染リスクの元を絶つことができ、結果的に地域全体の公衆衛生を守ることにもつながります。
まとめ|被害が出る前に、専門駆除で予防を
SFTSなどのマダニ媒介感染症は、アライグマやハクビシンといった害獣を介して拡大する恐れがあります。関東エリアの都市部でも既に感染事例が報告されており、感染後の治療には限界があるため、予防こそが最も重要な対策です。害獣駆除は、マダニのリスクを根本から断つ有効な手段です。専門業者の力を上手に活用して、早期対策を心がけましょう。